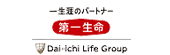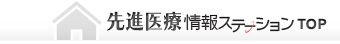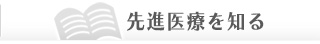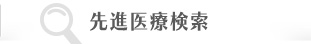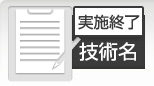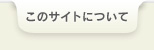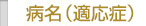 ライソゾーム病(ムコ多糖症I型およびII型、ゴーシェ病、ファブリ病ならびにポンペ病を除く。)
ライソゾーム病(ムコ多糖症I型およびII型、ゴーシェ病、ファブリ病ならびにポンペ病を除く。)
 ライソゾーム病は先天性代謝異常(生まれつき酵素の欠損などにより体内の代謝がうまくいかない病気)の一つで、進行性のため早期の診断治療が重要です。
ライソゾーム病は先天性代謝異常(生まれつき酵素の欠損などにより体内の代謝がうまくいかない病気)の一つで、進行性のため早期の診断治療が重要です。
培養細胞によるライソゾーム病の診断は、ライソゾーム病を胎児期もしくは新生児期に診断して早期治療につなげる技術で、先天性代謝異常が疑われる症状をもつ小児にも行われます。
胎児の場合は羊水を採取し、羊水細胞を培養後、細胞中の酵素活性を測定します。新生児や小児の場合は、末梢血を採取してリンパ球を培養、あるいは皮膚生検を行い、線維芽細胞を培養して、培養細胞中の酵素活性を測定します。
酵素活性の測定後、酵素補充療法の適応とならない場合は、造血幹細胞移植などのさまざまな治療法を行います。適切な治療法がない場合には、早期に対症療法や生活指導を行うことで患者さんのQOL(生活の質)の向上が期待できます。

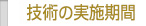 2008/07/01~2022/03/31
2008/07/01~2022/03/31

- 過去に承認されていた実施医療機関
都道府県 医療機関名 所在地 電話番号 医療機関の実施期間 大阪府 大阪公立大学医学部附属病院 
〒545-8586
大阪市阿倍野区旭町1-5-706-6645-2121 ~2022/03/31
本サイトで扱う情報は2012年9月21日以降に更新されたものとなります。「過去」の実施技術・医療機関は、 2012年9月21日以降に終了したものを掲載しています。