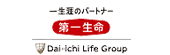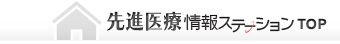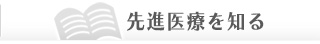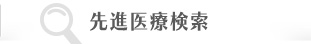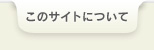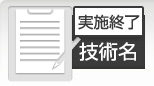
生体内吸収性高分子担体を用いた塩基性線維芽細胞増殖因子による血管新生療法
せいたいないきゅうしゅうせいこうぶんしたんたいをもちいた えんきせいせんいがさい ... >>
この技術は「2012年12月31日」で先進医療に該当しなくなりました。
|
|
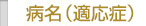 慢性閉塞性動脈硬化症またはバージャー病(いずれも従来の治療法による治療が困難なものに限る。)
慢性閉塞性動脈硬化症またはバージャー病(いずれも従来の治療法による治療が困難なものに限る。)
 慢性閉塞性動脈硬化症やバージャー病(閉塞性血栓血管炎)では、四肢の末端に血液が十分供給されないために組織に酸素が届かない「虚血症状」が起こります。これに対して標準的には、血行改善薬などの内科的治療や、下肢の血管拡張術・血栓除去術、動脈血栓除去術、血管移植術、バイパス移植術等の外科的治療が行われます。しかし、高齢化や糖尿病患者の増加に伴って慢性閉塞性動脈硬化症は増加しており、下肢切断に至るケースも多いのが実状です。
慢性閉塞性動脈硬化症やバージャー病(閉塞性血栓血管炎)では、四肢の末端に血液が十分供給されないために組織に酸素が届かない「虚血症状」が起こります。これに対して標準的には、血行改善薬などの内科的治療や、下肢の血管拡張術・血栓除去術、動脈血栓除去術、血管移植術、バイパス移植術等の外科的治療が行われます。しかし、高齢化や糖尿病患者の増加に伴って慢性閉塞性動脈硬化症は増加しており、下肢切断に至るケースも多いのが実状です。
血管新生療法は、虚血になっている部分の周辺組織から新しい血管を生じさせる、または近くの別の血管を発達させるという方法です。
この先進医療技術は、血管新生療法の中でも血管新生タンパクを投与するタンパク治療の1つで、トラフェルミン(塩基性線維芽細胞成長因子)とゼラチンハイドロゲル(生理活性を保った血管新生タンパクを含ませる)を注射剤として、虚血下肢の腓腹筋に注射します。
血管新生タンパクを病変部位に局所的に、十分かつ必要期間、作用させることができ、従来の、血管新生タンパクを全身へ大量・反復投与する方法で起こっていた副作用が回避されます。
この治療により、下肢切断を選択せざるを得なかった重症下肢虚血患者さんが、下肢切断を回避できることが期待されています。また、血管新生療法は他に、血管新生タンパクを発現する遺伝子を用いる「遺伝子治療」、血管新生を促す細胞を移植する「細胞移植治療」があります。

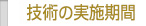 2010/07/01~2012/12/31
2010/07/01~2012/12/31

- 過去に承認されていた実施医療機関
都道府県 医療機関名 所在地 電話番号 医療機関の実施期間 京都府 京都大学医学部附属病院 
〒606-8507
京都市左京区聖護院川原町54075-751-3111 ~2012/12/31
本サイトで扱う情報は2012年9月21日以降に更新されたものとなります。「過去」の実施技術・医療機関は、 2012年9月21日以降に終了したものを掲載しています。